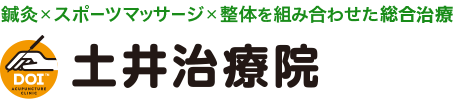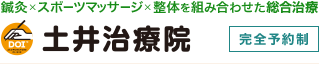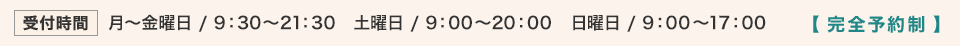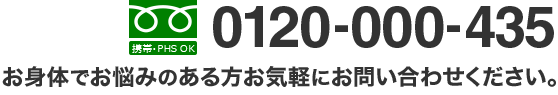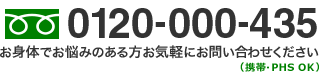筋肉が硬くなると変形性股関節症が悪化する?
 股関節(こかんせつ)の軟骨がすり減り、歩いている時の痛みを引き起こす変形性股関節症(へんけいせいこかんせつしょう)。初期には歩き初めの股関節の痛みですが、徐々に歩くたびに股関節が痛むようになり、いずれは動くたびに股関節に強い痛みを引き起こし日常生活にも支障が及ぼすほどの痛みを引き起こします。症状が進行すると人工関節置換術という手術をおこなうこともあります。変形性股関節症は退行性病変と言い、ほうっておくと徐々に症状は進行していってしまいます。手術をせずに変形性股関節症と付き合うには股関節の状態を維持する治療やご自分でのリハビリなどが重要になってきます。
股関節(こかんせつ)の軟骨がすり減り、歩いている時の痛みを引き起こす変形性股関節症(へんけいせいこかんせつしょう)。初期には歩き初めの股関節の痛みですが、徐々に歩くたびに股関節が痛むようになり、いずれは動くたびに股関節に強い痛みを引き起こし日常生活にも支障が及ぼすほどの痛みを引き起こします。症状が進行すると人工関節置換術という手術をおこなうこともあります。変形性股関節症は退行性病変と言い、ほうっておくと徐々に症状は進行していってしまいます。手術をせずに変形性股関節症と付き合うには股関節の状態を維持する治療やご自分でのリハビリなどが重要になってきます。変形性股関節症は「加齢により軟骨がすり減って痛みを引き起こす」と言われています。あとは体重による負荷も原因ともいわれています。これらも一つの原因ですが股関節周りの筋肉もとても関連が深いです。股関節周りの筋肉が硬くなってしまうと変形性股関節症を悪化させることになります。
股関節の内旋筋群と外旋筋群が硬くなると変形性股関節症を悪化させる
股関節は人体でもっとも大きな関節であるためたくさんの筋肉が股関節を通ります。股関節は・足を上に上げる(屈曲)
・足を後ろに上げる(伸展)
・足を外側に上げる(外転)
・足を内側に上げる(内転)
・足を内側に回す。回旋する(内旋)
・足を外側へ回す。回旋する(外旋)
と様々な動きができる関節です。これは球関節(きゅうかんせつ)という関節の特徴です。股関節はたくさんの動きができますがそれぞれの動きで使う筋肉は変わります。その中で、足を内側へ回旋する(内旋)筋肉、足を外側へ回旋する(外旋)筋肉が硬くなると変形性股関節症を悪化させます。
股関節の内旋をする筋肉
 股関節を内側へ回旋する(内旋)する筋肉は中臀筋(ちゅうでんきん)、小殿筋(しょうでんきん)、大腿筋膜張筋(だいたいきんまくちょうきん)という筋肉です。単純に場所を説明すると股関節の外側付近に付着する筋肉です。
股関節を内側へ回旋する(内旋)する筋肉は中臀筋(ちゅうでんきん)、小殿筋(しょうでんきん)、大腿筋膜張筋(だいたいきんまくちょうきん)という筋肉です。単純に場所を説明すると股関節の外側付近に付着する筋肉です。中殿筋(ちゅうでんきん)
起始:腸骨(ちょうこつ)の臀筋面(でんきんめん)
停止:上部線維 腸脛靱帯(ちょうけいじんたい
 下部線維 大腿骨大転子(だいたいこつだいてんし)の外側面
下部線維 大腿骨大転子(だいたいこつだいてんし)の外側面※起始とは筋肉が始めにくっつく場所、停止とは筋肉が最後にくっつく場所
小殿筋(しょうでんきん)
起始:腸骨(ちょうこつ)の臀筋面(中殿筋の起始の下方)
停止:大腿骨の大転子の外側面
大腿筋膜張筋(だいたいきんまくちょうきん)
起始:上前腸骨棘(じょうぜんちょうこつきょく)
停止:腸脛靱帯(ちょうけいじんたい)
中殿筋(ちゅうでんきん)、大腿筋膜張筋(だいたいきんまくちょうきん)は皮膚の下に触れることのできる筋肉ですが小殿筋(しょうでんきん)は中殿筋(ちゅうでんきん)に覆われるため皮膚の下に触れることができず、中臀筋(ちゅうでんきん)を介して触れるような形になります。
これら3つの内旋筋群が収縮、痙縮(筋肉が緊張して縮まっている状態)すると股関節の関節の隙間を狭めてしまいます。関節の隙間が狭まると軟骨同士がぶつかりやすくなり変形性股関節症を増強します。
股関節を外旋する筋肉
 股関節を外側に回す(外旋)筋肉は梨状筋(りじょうきん)、上・下双子筋(じょう・かそうしきん)、内閉鎖筋(ないへいさきん)、外閉鎖筋(がいへいさきん)大腿方形筋(だいたいほうけいきん)です。これらの筋肉の単純な場所をいうと股関節の後ろ側に付着する筋肉です。
股関節を外側に回す(外旋)筋肉は梨状筋(りじょうきん)、上・下双子筋(じょう・かそうしきん)、内閉鎖筋(ないへいさきん)、外閉鎖筋(がいへいさきん)大腿方形筋(だいたいほうけいきん)です。これらの筋肉の単純な場所をいうと股関節の後ろ側に付着する筋肉です。他に大殿筋も外旋作用がありますが変形性股関節症とかかわりの深い筋肉は上記の6つの筋肉です。
梨状筋(りじょうきん)
起始:仙骨の骨盤面(仙骨前面外側)
停止:大腿骨の大転子の先端
上・下双子筋(じょう・かそうしきん)
起始:上双子筋→坐骨棘(ざこつきょく) 下双子筋(坐骨結節)
停止:内閉鎖筋(ないへいさきん)の停止腱と合体して転子窩(てんしか)
内閉鎖筋(ないへいさきん)
起始:閉鎖膜(へいさまく)と閉鎖孔外周(へいさこうがいしゅう)の内側面
停止:大腿骨の転子窩(てんしか)
大腿方形筋(だいたいほうけいきん)
起始:坐骨結節(ざこつけっせつ)の外側縁
停止:大腿骨の転子間稜
外閉鎖筋(がいへいさきん)
起始:閉鎖膜(へいさまく)と閉鎖孔外周(へいさこうがいしゅう)の外側面
停止:大腿骨の転子窩(てんしか)
難しい話になってしまいましたがこれらの筋肉の起始、停止は覚える必要はありません。だいたいここら辺の位置にあるなということを頭にいれておいてください。
上記の外旋筋群(がいせんきんぐん)も収縮、痙縮すると股関節の隙間を狭めてしまいます。股関節の隙間が狭まってしまうと軟骨同士がぶつかりやすくなり変形性股関節症を悪化させてしまう事になります。
股関節の内旋筋群、外旋筋群を緩ますことが大事
上記でも説明したように股関節の内旋筋群と外旋筋群が収縮、痙縮(けいしゅく)すると股関節の隙間が狭まって軟骨がぶつかりやすくなってしまい、変形性股関節症が悪化させてしまいます。それを防ぐためにも内旋筋群、外旋筋群の筋肉を柔らかくする必要があります。筋肉を緩ます方法は鍼治療やマッサージ、整体法など様々ありますがしっかりと内旋筋群、外旋筋群にアプローチする必要があります。現在、変形性股関節症でどこか医療機関に受診しているのでしたら「内旋筋群、外旋筋群を緩ませてください」とお願いしてみてください。その際に「よくご存じですね」といわれたらその医療機関は股関節の治療に対して最低限の知識を要していると思います。逆に「?」という反応であったら他の医療機関に変更したほうが良いかもしれません。変形性股関節症に対しての知識があまりない可能性が高いです。
内旋筋群は股関節の外側、内旋筋群は股関節の後ろ側にあります。股関節の外側、後ろ側の筋肉を緩ますことをしてくれているかを確認しながら治療を受けてみてください。
これらの筋肉を直接緩ますようなアプローチ(直接マッサージするなど)をしなくても筋肉を緩ます治療法は様々あります。なので直接その場所に触れることが大事ではないのですが、直接でも間接的にでも緩ますアプローチをすることは非常に重要です。